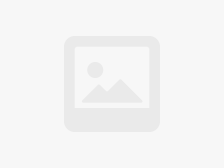関連検索ワード
・正しくは「杉菜(すぎな)」の 胞子茎(ほうしけい)と いうもので、 「付子」とも書く。 食べられる(油いため)。 この土筆に引き続いて、 細い線状の 緑の葉っぱが出 ...
日本に生育するトクサ類では最も小柄である。一般的には栄養茎をスギナ、胞子茎をツクシ(土筆、筆頭菜)と呼び分けることがある ...
シダ性植物の多年草。早春に出てくる胞子茎をツクシ、栄養茎をスギナと呼びます。スギナを乾燥させたものがモンケイ「問荊」で、利尿などに用います。
デジタル大辞泉 - 土筆の用語解説 - 早春に出るスギナの胞子茎。筆状で淡褐色、節に「はかま」とよぶ葉がつく。頂部から胞子を出すと枯れる。食用。筆頭菜ひっとうさい ...
2022/3/31 -つくしのほろ苦さと、にんにくの香りが食欲をそそる炒め物です。豚バラ肉を加えることで、ご飯にぴったりなおかずに仕上がります。
ツクシの名前は、地上に突き出るように芽を出す姿から生まれました。「土頭菜」「土筆」「土筆菜」「筆の花」などと書き、「つくしんぼ」と呼ぶこともあります。いずれも ...
2024/2/29 -つくしは、春になると地上に出てきて、なんと1日約1センチのペースでぐんぐん成長します。10~15センチの長さに達すると「胞子のう症」という六角形の ...
早春に出るスギナの胞子茎。筆状で淡褐色、節に「はかま」とよぶ葉がつく。頂部から胞子を出すと枯れる。食用。筆頭菜 (ひっとうさい) 。つくづくし。つくしんぼ。
筆和、土筆飯、土筆汁トクサ科の多年草。杉菜の胞子茎をいう。三月ごろから日のあたる土手や畦道に生える。筆のような形をしているのでこの名がある。
名詞 編集 · 中国画の下書きに用いた柳の先を焼いて炭にしたもの。 · (熟字訓で「つくし」とも)「つくし」の異称、なお、漢名は「筆草」。
スギナ
スギナ(杉菜、接続草、学名: Equisetum arvense)は、シダ植物門トクサ綱トクサ目トクサ科トクサ属の植物の1種。日本に生育するトクサ類では最も小柄である。一般的には栄養茎をスギナ、胞子茎をツクシ(土筆、筆頭菜)と呼び分けることがある。-Wikipedia