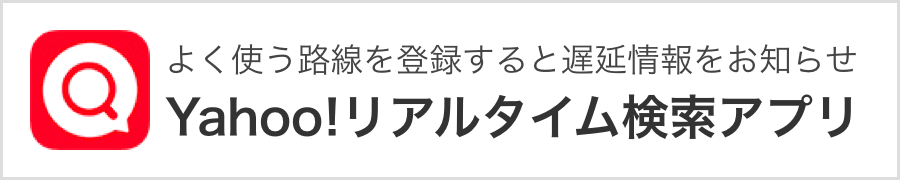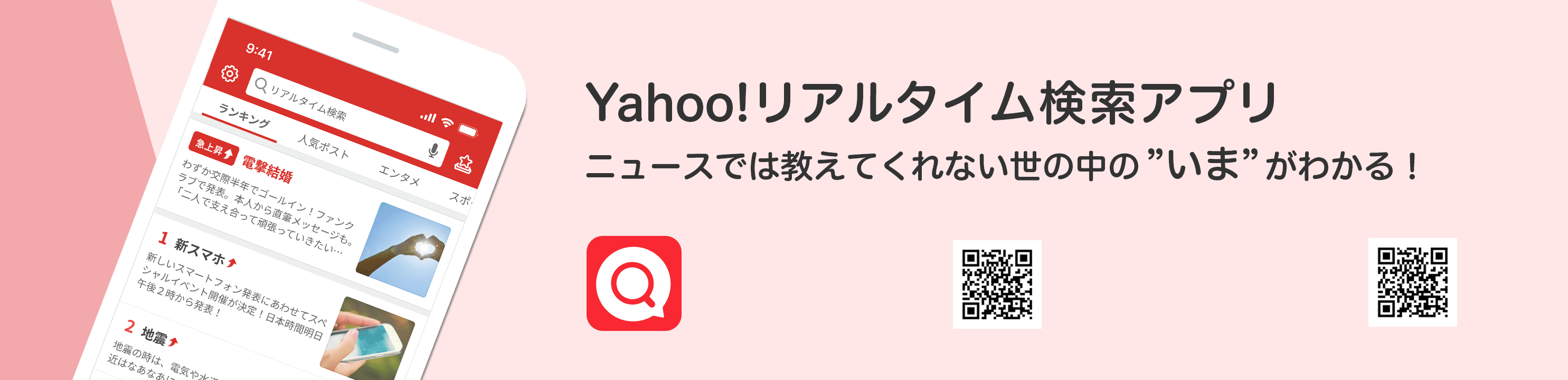ポスト
「予(豫)」も「預」も「あらかじめ」で「預言」で未来をいいあてることですね。 例えば穀梁伝序「『左氏』豔而富、其失也巫。」に対する唐初の楊士勛の疏(注釈)に、「巫者謂多敘鬼神之事、預言禍福之期」(「巫」というのは多く鬼神の事を記したり、禍福の怒る時期を預言したりすることだ)
メニューを開く私は「予言」と「預言」の使い間違いに結構注目してるんだけど、これも数十年単位で間違えられ続けてれば「預言」の方にも「未来を言い当てること」の意味がつくんじゃないかと思ってる 「預言」の方が画数多いし神秘的だし仰々しい感じがするから、こっちの漢字を「予言」の意で選択するのかな?
みんなのコメント
メニューを開く
とあるように、英語でいうprophecyの訳語に使われるはるか以前から、漢語で「あらかじめ言う」の意味で使われてきた言葉ですね。(漢語の「預」は「参加する」という意味で「あずかる」とも読みますが、「他人のものを保管する」という意味で「あずかる」と読むのは日本独自の用法)