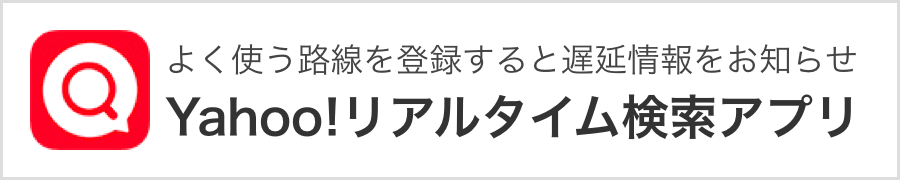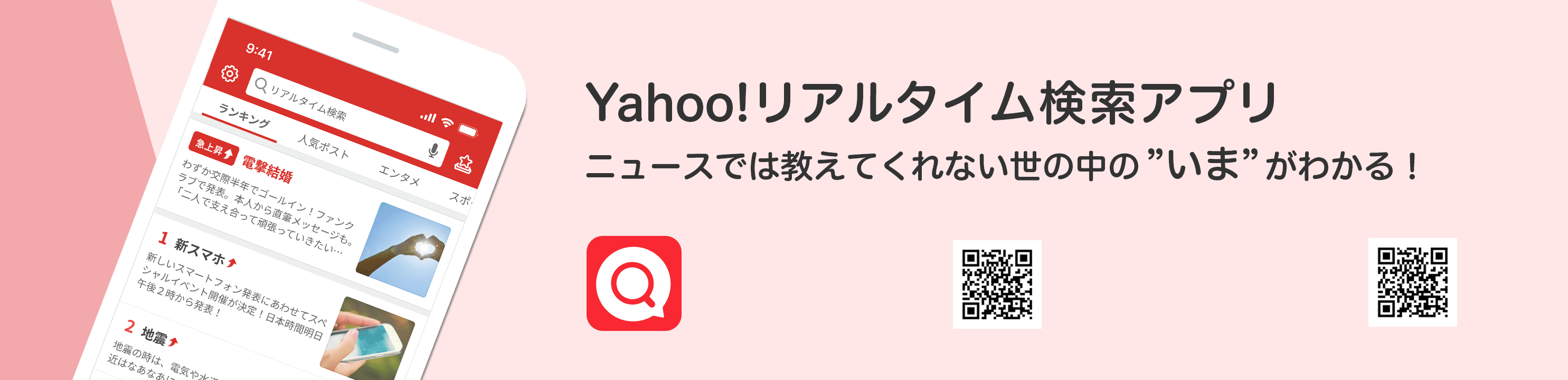ポスト
「預」を「あずける」と読むのは国訓なのか。「預」が「与」の通仮字として用いられ、「関与する」の「あずかる」の意味で使われるため、同音意義語の物を預けるの「あずける」にも転用されたんだな。中国語では「預」は「予」と同義で、現代中国語だと「預計」は未来を予測するという意味になる。
メニューを開く「予(豫)」も「預」も「あらかじめ」で「預言」で未来をいいあてることですね。 例えば穀梁伝序「『左氏』豔而富、其失也巫。」に対する唐初の楊士勛の疏(注釈)に、「巫者謂多敘鬼神之事、預言禍福之期」(「巫」というのは多く鬼神の事を記したり、禍福の怒る時期を預言したりすることだ)
みんなのコメント
メニューを開く
同様の国訓の例には「頂」を、「受領する」という意味の「いただく」と訓じるものがある。これは同音異義語の「頭上にささげ持つ」という意味の「いただく」からの「仮借」である。「プレゼントを頂いた」と、「お金を預ける」は、漢字本来の使い方からすると、同じくらいの間違っていることになる。
人気ポスト
今日はピリ辛甘ダレの棒棒鶏定食を食べました。おいしかったです。
想定外のところ
周りに出産報告の連絡してたら、職場への報告LINEでお昼ご飯産んでしまった…
【ご報告】 私事ですが、この度購入したピンバッチが納品されました。 これからも一緒に楽しい時間を過ごせるよう頑張りたい所存です。
18才で既に20人のチンボ咥えてるのは将来性◎ 軽率にパコらせてほしい
予防注射を頑張って無言で耐えたワンコがこちらです
原作を改変せずにオリジナル展開でも評価され人気シリーズとして不動の地位を築いた実写ドラマの例↓
#誰が本物連れてこいと言ったよとなったキャラ っていうお題が流れてきパッと頭に浮かんだ4人
もうスパムだろこれ
トレンド19:44更新
- 1
エミリエ
- 新キャラ
- 2
アニメ・ゲーム
増山江威子さん
- 声優・増山江威子さん
- 増山さん
- 不二子ちゃん
- キューティーハニー
- 峰不二子
- ルパン三世
- 天才バカボン
- バカボンのママ
- 増山江威子
- ご冥福をお祈り
- 申し上げます
- 89歳
- 不二子ちゃーん
- いただきました
- ハニー
- バカボン
- 3
ニュース
甲斐田晴
- にじさんじ
- 誹謗中傷
- 甲斐田
- 損害賠償
- 4
アニメ・ゲーム
しゅごキャラ
- なかよし
- 5
アニメ・ゲーム
ピノコニー
- さよならピノコニー
- YouTube
- 6
アニメ・ゲーム
セリカ
- ご確認ください
- 7
エンタメ
庭ラジ
- 海人くん
- 海ちゃん
- ケイタ
- 髙橋海人
- 8
アニメ・ゲーム
ゆぐゆぐ
- マグナ3
- 9
グルメ
スイーツパラダイス
- スイパラ
- ブレイバーン
- イラスト
- 10
虫の画像
- 無断加工
- 推しの扱い粗末
- 推しの扱い
- 書類送検
- 著作権法違反
- 25歳