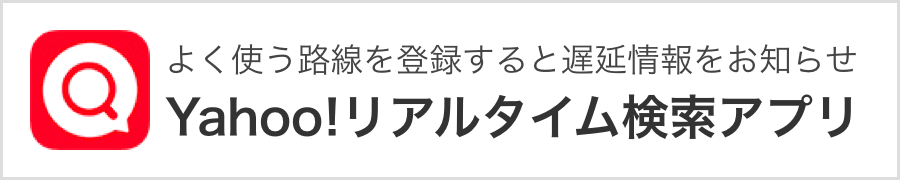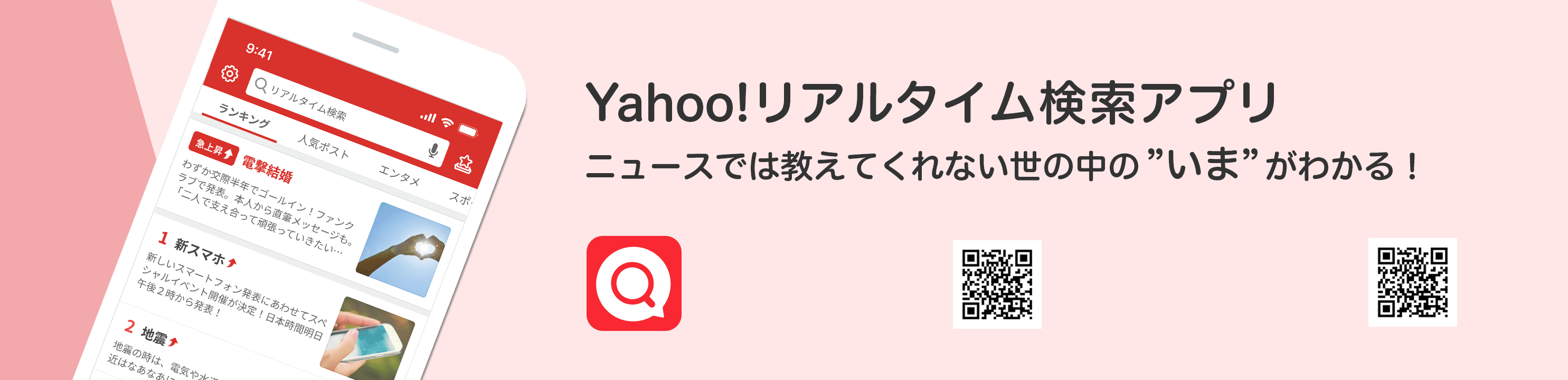ポスト
物価上昇率と労働分配率は逆の動きをする傾向がある。一方、CPIが高いと中小企業は価格転嫁しやすい。 交易条件悪化の所得が流出を、国内中小が持つか労働者側が持つかだけのことで。 デフレがなぜ悪いかの説明で物価が上がらないと企業収益悪化し、賃金も落ちると言う説明の意味のなさはここにある。 pic.twitter.com/qo1Af4PSG7
メニューを開くみんなのコメント
メニューを開く
デフレがなぜ悪いのかという典型的な図。 給与減少でモノを買わなくなるのところで理屈が破綻している。 デフレは物価水準全体を落とすので実質賃金にも実質利益にも影響を与えない。ただ、実質賃金を上げて、企業の利益を相対的に減らす効果ならある。 結論を言えばデフレは不況の結果にすぎない。 pic.twitter.com/lTA0Of1Jl0
メニューを開く
補足すると、これは企業が価格転嫁できても、自社の利益上昇分よりも小さい額でしか名目賃金を上げないからだが。 別の視点で言えば、CPIに対するインフレ目標は交易条件悪化による所得流出を見えなくし、単に国内の所得配分の変更だけを目指した政策とも言える。