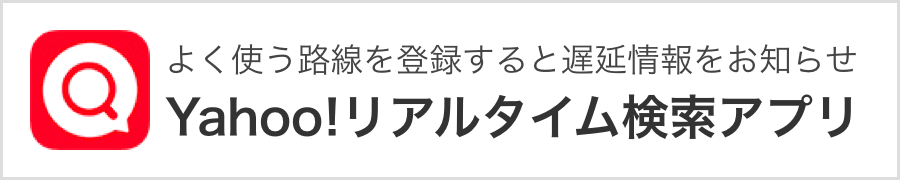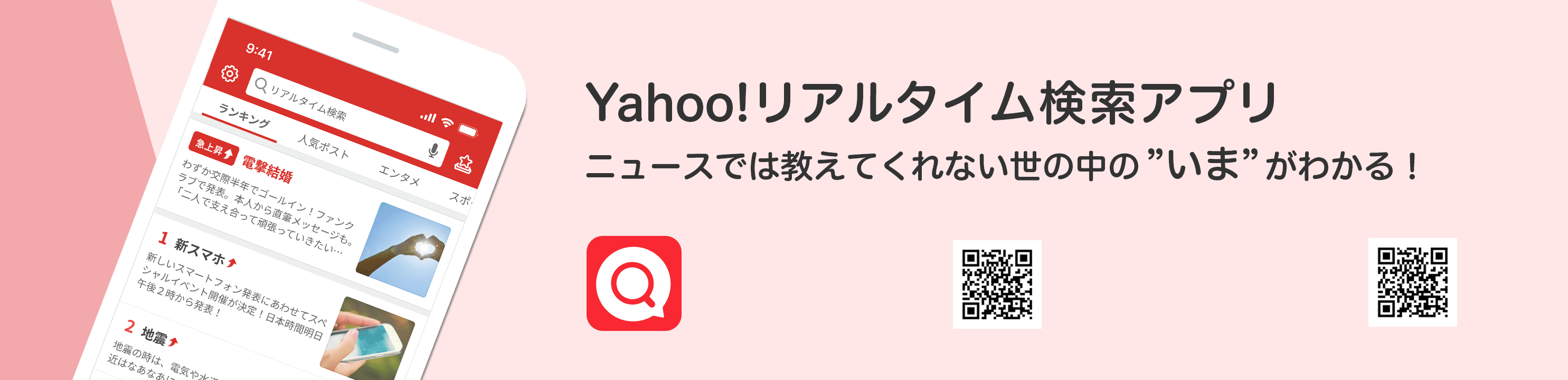ポスト
家形埴輪の中には、その壁材の木に、草壁を取り付けた表現もあるとのことで、そうした壁は、考古学者の穂積裕昌さんが講座で話した内容によると、古代の大嘗祭の建物の起源でもあるとのことです。
メニューを開くみんなのコメント
メニューを開く
そのため、当時の掘立柱建物には、格子状の木枠があった訳でして、「トノ」の解釈しだいですが、当時の掘立柱建物は、とくに建築中には、柱の組み合わせから格子状の木枠まで、「あみ」や「つな」のように木が組まれた芸術的存在であり、繊維の「あみ・つな」が綱、木の「あみ・つな」が殿なのでは?
人気ポスト
そうはならんやろ
大阪の天満橋駅近くにある「Masahiko Ozumi Paris」ではニットで包まれたような可愛いフォルムのザブトンモンブランが提供される。 口に入れた途端に栗の風味が広がりショコラムースがアクセントになってなめらかな舌触りでとろけます! お土産で持っていくと間違いなく喜ばれる一品です🌰
タイのコンビニにはこれが当たり前にあるの羨ましい。 美味すぎる。
昨日奥多摩のビジターセンターで見たダニの仕組み。「唾液の注入と吸血を繰り返します」「赤血球以外は吐き戻します」「唾液腺 麻酔を皮膚に注入する。病原体はここで増えます」「セメント質 マダニ自身を皮膚に固定する」などのパワーワードが並んでいて絶対刺されたくないと思った。
知ってるか?今日で5月が終わりなんだってさ。6月は祝日がないんだってさ。まじかよ。
【悲報】作中やべー奴ランキングトップランカーの後藤美智代、またも周囲に圧倒的な差をつけてしまう。
蓮舫氏のネガキャンに必死な古市と岩田 古市「今回、蓮舫議員は参議院を辞めるようですが、仮に都知事選を落選しても『衆議院に鞍替え』という話も聞くので、あまり『リスクを取ってない』と見える」 岩田明子「蓮舫氏は負けてもあまりリスクがない…」 ↓ #めざまし8 #蓮舫がんばれ
愛する妹から風呂の忠告されて興奮🤩
【SNS震撼】マクドナルドを「定食」として楽しむ猛者現る news.livedoor.com/article/detail… 「当時1週間毎日マックを食べる生活をしていて、5日目くらいにハンバーガー以外のものを食べたい思いマック定食を作りました」とのこと。なお、黒く濁った"汁物"の正体はコーラだという。
トレンド13:27更新
- 1
ニュース
古舘伊知郎さん
- スポーツ王
- にじさんじスポーツ王
- 古舘伊知郎
- 2024年6月
- にじさんじ
- レオス
- 2024年
- プレミア
- 2
危機契約
- ステージ
- 3
草薙寧々
- 花里みのり
- 巡音ルカ
- ルカ
- ヘアスタイル
- 寧々
- 4
ニュース
公開手配
- タクシー拳銃
- 瀬川川好一
- 職業不詳
- 反省してください
- 埼玉
- タクシー強盗
- タクシー運転手
- 5
ITビジネス
騎乗停止
- 水沼元輝
- スマホ使用
- 調整ルーム
- 重大な非行
- 持ち込み禁止
- 東京競馬場
- 注意義務
- 水沼
- JRA
- スマホ
- 6
星導ショウ
- 7
アニメ・ゲーム
プリンセスメーカー2
- バストサイズ
- 父と結婚
- 執事との結婚
- 父との結婚
- プリンセスメーカー
- PS5版
- 発売延期
- 結婚エンド
- PS5
- PS4
- 削除します
- Switch
- PS
- 8
にじぬい
- 9
ITビジネス
加工屋の娘
- 筆頭ランサー
- MH4
- イャンクック
- ワイルズ
- 10
エンタメ
全員オフ
- 隠しカメラ
- 到着を待って
- バーベキュー
- ゲリラインライ
- BBQ
- 9時40分
- しょっぴー
- 仲良しすぎ
- SnowMan
- オフ
- インスタライブ