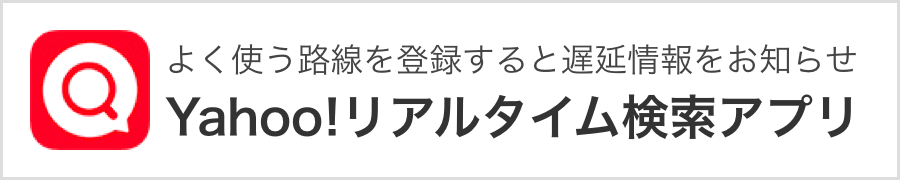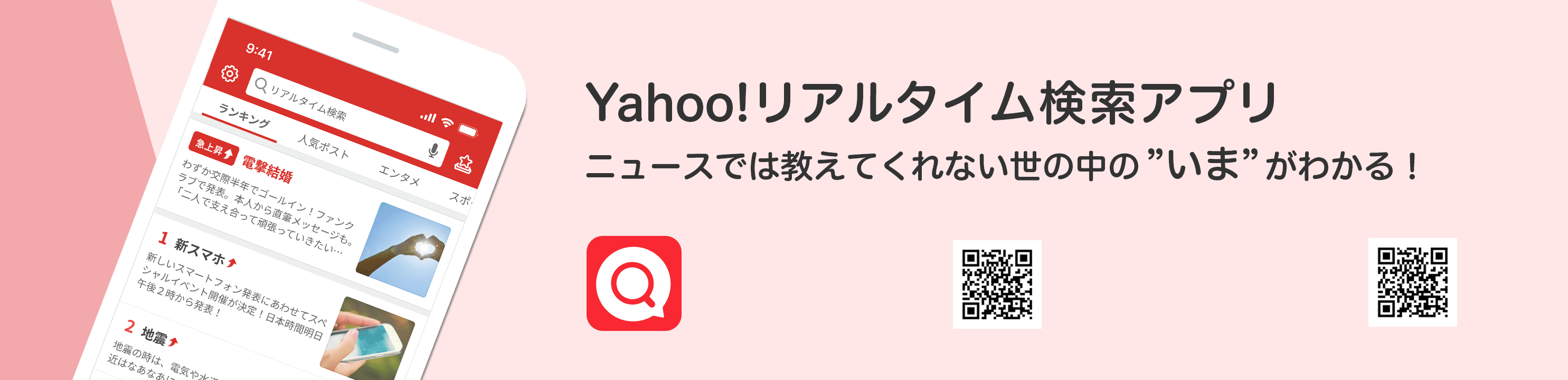ポスト
ちなみに、実際に機能した標準規格として音溝形状・再生針形状の定義は米国放送局向けの1949年NAB規格(左)が初で、この時はワイドグルーヴのみ。 1953年NARTB規格(右)で初めてファイングルーヴ(マイクログルーヴ)向けも定義されました。このタイミングでは「1mil stylus」と明記されています。 pic.twitter.com/AEu0dBSnhC
メニューを開く0.7mil / 1mil 交換針が選べるってのは(気分的に)なんか嬉しいですね。 で、民生用としては、RIAA規格が策定されるまでは、溝の角度(90°±5°)溝底面の半径(最大 0.006mm)その他諸々も、録音機材毎スタジオ毎にバラバラだったので、再生時どのスペックがベストかも様々だったんですよね。
みんなのコメント
メニューを開く
更に言うと、戦前は、カッター針のサイズや形状などカッティング時の各種技術は、企業秘密的になんの共有もされていませんでしたので、各スタジオごとにバラバラの溝形状だったりしました。 民生用レコードの情報公開・共有および規格標準化に本格的に動き出したのは戦後で、Electronic Industries… pic.twitter.com/Tib8HS5AH1
人気ポスト
注射の激痛に耐えながら速報です。
5月15日、21日、22日に千葉県の小学6年生約6000名が東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」に来園しました。olc.co.jp/ja/topics/pr_t…
手を痛めてレントゲン撮ったんだけど可愛いすぎて先生と一緒に笑ったww
お前らここで「おっふ」ってなったろ
売る気なくて草
最近の子は怖いよ。
この顔で毎日学校行けるの羨ましすぎて死にそう
おい、毎朝シャーペンでガリガリ蚯蚓脹れつくって小学校行ってた時の写真出てきて笑えない。散々ガキ馬鹿にしてきたけどお前特級呪物やないか
婚約指輪のダイヤモンドの大きさに悩んでいたら参考にどうぞ ※モデル薬指指サイズ9号
トレンド4:56更新
- 1
ニュース
豊後水道
- M4.5
- M4.3
- M4.4
- 震度4
- 気象庁の
- 地震の規模
- 震度3
- 緊急地震速報
- 津波の心配は
- 津波の心配はありません
- 震源の深さ
- 最大震度4
- 地震情報
- M3
- 地震速報
- 2024年6月
- 2
朝生
- 小幡績
- 加谷
- 加谷珪一
- 田中れいか
- 吉田はるみ
- 牧原秀樹
- 3
ニュース
高知県西部
- 愛媛県南予
- 震度4
- 地震情報
- 4
アニメ・ゲーム
漫画図書館Z
- カード会社
- 5
エンタメ
大人の歌謡クラブ
- 6
482億円
- 482億
- DMMビットコイン
- Bitcoin
- 不正流出
- 全額保証
- DMM Bitcoin
- ビットコイン
- ビットコイン流出
- グループ会社
- BTC
- 7
志乃原菜摘
- 激走戦隊カーレンジャー
- 本橋由香
- イエローレーサー
- 46歳
- 8
ニュース
豊後水道で地震
- 緊急地震速報
- 9
ハイスピードエトワール
- ハイスピ
- 第9話
- MBS
- イラスト
- 10
高知県宿毛市
- M4.5
- 津波の心配は
- 津波の心配はありません
- 地震情報