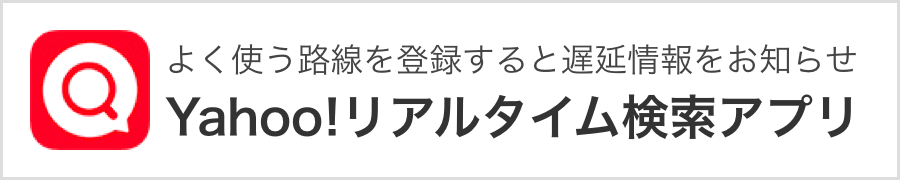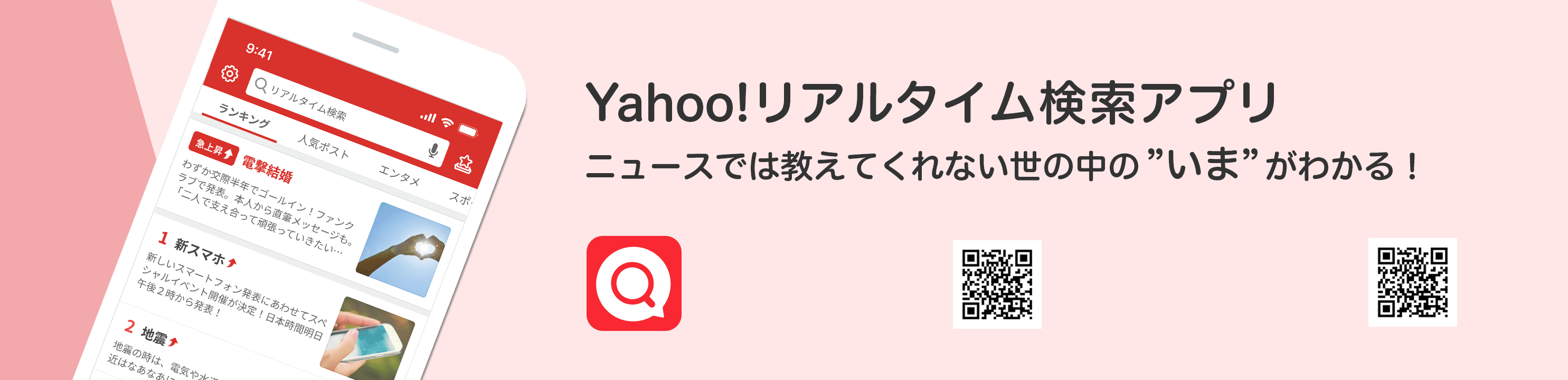ポスト
文部科学大臣の諮問が出たローマ字問題。国語課題小委員会の時点から現状認識がおかしい。 A「訓令式が(国民に)定着していない」ことを指摘し、例としてB「パスポートや道路標識」を挙げている。しかし普通に考えれば「Aの例がB」ではなく、「Bの結果がA」だろう。 bunka.go.jp/seisaku/bunkas… pic.twitter.com/DLjct70ztQ
メニューを開くみんなのコメント
普通、そうした事情背景は読み取れません。 よほどそうしたことに通じているか、経緯が説明されない限り分からないでしょう。 駅の表示にヘボン式が猛然とアタックかけたというのも調べてみないと見当もつかないでしょう。 でも、だからそうなったという証明にはならない。 そこは立体的に表現しないと
「Aの原因でありそれ自体でもある例がB」のように思います。 パスポート等での採用されたこと自体も訓令式が定着したとは言えない例だし、 パスポート等で採用されたのが原因で、その結果として、その他でも訓令式が定着したとは言えないでしょう。
論理展開において、何か不備や瑕疵があるのでしょうか? 歴史的背景で訓令式とヘボン式の間でせめぎ合いとかつばぜり合い、そうしたものによる影響はありましたか? 不服の弁として、こうだろうというところを述べて頂かないと何を訴えたいのか理解出来ません。 単に論理学の問題でもないでしょう。
もひとつ何を問題にしたいのかよく分かりません。 内閣告示において当初想定していた事が達成されていないということですね! その役目は訓令式に託されていた。 そして、その想定とは『国民がローマ字を用いて国語の文や文章をつづること』だったようです。 それで、何がどうしたと言うのでしょう。
「英語に準じたとも言えるローマ字が国際社会で用いられるようになり、国内にもその影響が及んでいる」という指摘もずれている。まるで海外ではじめに考案され使われ出したかのような言い方だが、そのjudoやmatchaという表記は日本人が積極的に使い出したもので、海外の人はそれを真似しているだけ。 pic.twitter.com/JXAbenZY18