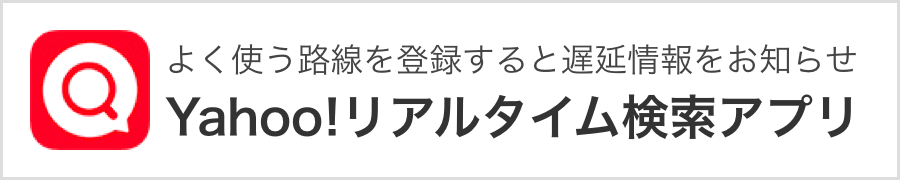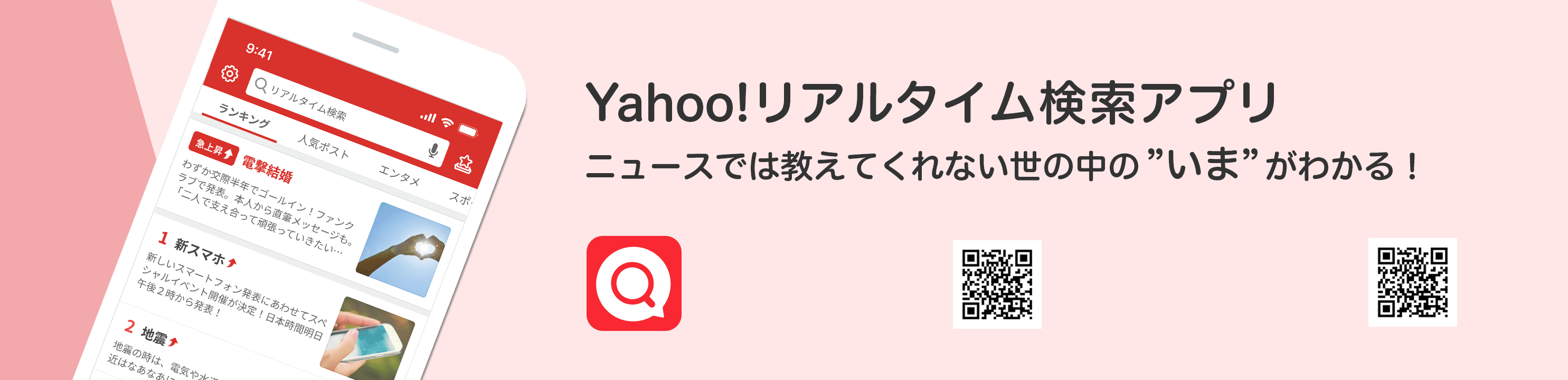ポスト
生徒から係り結びについて質問が増え、 その発生メカニズムを調べています。 係助詞「ぞ」の興味深いエピソード。 奈良時代以前の日本語において、 存在を表す唯一の語だったようです。 なんと否定形や推量形が無かったとか。 (「ぞ」に打ち消しの「ず」は付かない) その後、漢文の翻訳などで pic.twitter.com/5aTgomBi3M
メニューを開くみんなのコメント
メニューを開く
“A is NOT B”と表現せざるを得なくなり、 存在を意味する動詞「あり」を改造して 「Aにあらず」 「Aにあらば」 で否定や推量を表すようになったとか。 外国語との接触で、 日本人は新たな表現を獲得した──。 現代日本語の「乱れ」を考える 面白いエピソードで「あり」ました🤩
人気ポスト
歩くと鳴る靴を履いてるのかもしれない
#これでフォロワーが増えました 初めて聞いた救急車のサイレンにびっくりして飛び上がり、ママに駆け寄っちゃうポメラニアンの赤ちゃん
ねぇこれ2,500円もしたっけ??????!!!!
←番組で作った 家→
ボーナスの時期に思い出したい言葉、第一位です。
こういうのすぐ連想できる人になりたい
と或る夜、やや賑やかな祖師ヶ谷商店街の狭い道に一台の超超超高級車が徐行して近づいてくる。 ハッキリ言ってウキまくり!笑 乗ってらっしゃったのは、俺の恩師であり育ての親である、#北野武監督。 #寺島進
モスが狂気のスタンプ出してるわね
バンクーバー水族館の飼育員さんの投稿見て心臓掴まれたかと思った、動画も可愛すぎる。普通に食べたいし。
トレンド21:21更新
- 1
アニメ・ゲーム
審神者証
- 役職追加
- 免許不携帯
- 審神者
- フレンド機能
- 2
アニメ・ゲーム
阿曇磯良
- アルターエゴ
- ひびき
- あづみのいそら
- ドラゴンキャッスル
- 神功皇后
- 千鍵
- 担当させていただきました
- 3
エンタメ
ランキングダービー
- それスノ
- ひみつの嵐ちゃん
- 嵐ちゃん
- Snow Man
- 二宮和也
- 4
アニメ・ゲーム
ひびちか
- アーネンエルベ
- ひびき
- あづみのいそら
- まほ箱
- 魔法使いの箱
- 千鍵
- まほよ
- ガラケー
- BGM
- 5
アニメ・ゲーム
オベロン
- 天草四郎
- 織田信長
- 晴信
- 6
エンタメ
マネキンファイブ
- ダブルパーカー
- マネキン
- 嵐ちゃん
- 翔ちゃん
- 7
ニュース
トラックの前
- 巻き込まれた
- すり抜け
- ご冥福をお祈り
- 8
アニメ・ゲーム
清姫
- ドラゴンキャッスル
- 霊衣
- 9
エンタメ
めざましどようび
- 10
せーはす
- 新入生歓迎会