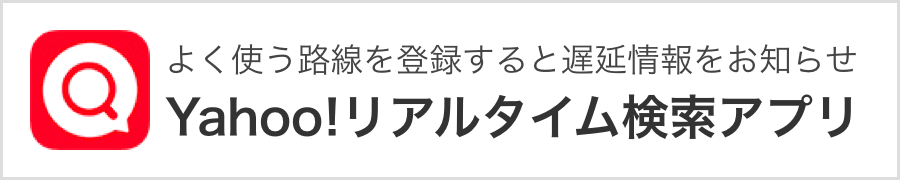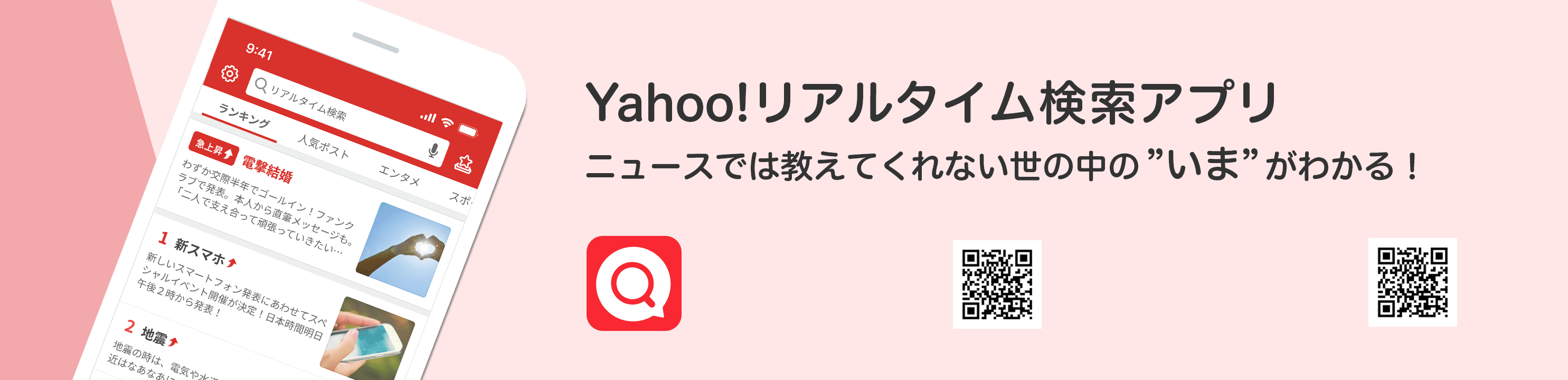ポスト
大伴太持が詠んだ「冬肥えて 夏瘠けれぬ 十年貫 我が身の重き 信じきものそ」ですね。 現代語訳:冬に太るものの夏に痩せきれない。それが十年も続いたら十貫になってしまった。いま私の身体は自分でも信じられないほどに重い。 ただ万葉集の時代では1貫3.75㎏ですから、太持は37.5㎏の増加ですね() x.com/taojiao_chan/s…
メニューを開くみんなのコメント
メニューを開く
奈良時代に10年の体重増加を嘆いた歌はありませんが、平安時代には「肥満に悩んでいた藤原朝成という貴族が、医師に減量の相談をしたところ、水飯(冷水をかけた御飯※お水漬け)を勧められた。しかし鮎の熟れ鮨やウリの干物を副食にして水飯を食べたら、美味すぎて余計に太った」という話はあります。 pic.x.com/PXZtBN1suC
メニューを開く
この歌って本当にあったんでしょうか?探したのですが見つけられず。こちらの資料によると "戯奴がため我が手もすまに春の野に抜ける茅花そ食して肥えませ" という歌が家持に贈られており、 "万葉集中で「肥える」という表現は、この歌以外では使われていない" とあります。 repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonip…