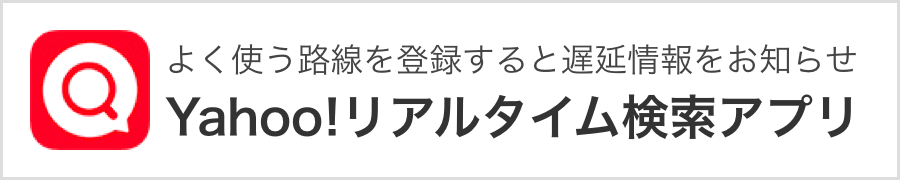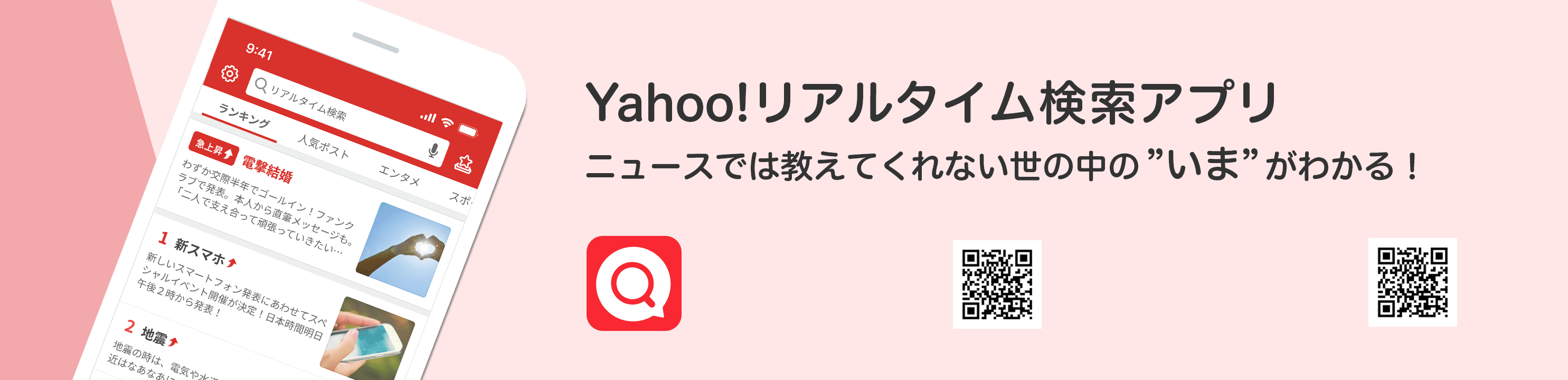ポスト
戸籍に関して 戸籍謄本、除籍謄本を追っていくことで、戸籍法が制定された明治4年頃の先祖まで遡れる。それ以前を探るには墓石や寺の過去帳を調査することになるが、それはさておき、明治6年1月の徴兵令制定が曲者で、国民を徴兵できる法律だが、戸主や長男は徴兵免除となっていた。
メニューを開くみんなのコメント
・江戸時代生まれの先祖を容易に辿れるのは戸籍法制定のおかげ ・戸籍法実施初期には穴多数だったが150年を経て確実性の高いものになっている筈 余談ですが、これは父方の祖父の系図で、父方の祖母は桓武天皇まで繋がっています(笑) 母方は代々農家なので特に面白くない系図です。
父から、ルーツは島川さんで徴兵逃れに近所の断絶した籍を復活させたと朧げに聞いてはいたが、4代前が戸籍乗っ取りで整合性取れちまった。 なんだかなぁ、まぁ全国的に多発したようだし、仕方ないか… ということで、 ・戸籍法は徴兵制のための名簿作り ・庶民は法の未整備を突き徴兵逃れ
年齢的にも安政生まれの長男與四郎だと上の記事にも沿うはず。 ちなみに本家の墓は大正8年に建てられており、建てたのは2代與四郎。 長男與四郎の子、銀次郎が、大正8年の與四郎の死後すぐに與四郎に改名しており、彼が2代と名乗ったのであれば、長男與四郎が初代となり、整合性も取れている。
次男以降だったご先祖が、絶家再興したと聞いている。 明治初期の除籍謄本見ると、前戸主、亡父與四郎の長男が戸主與四郎となっていて、戸籍に母の記載がない。 たぶん戸籍制度開始初期の謄本なので、記載事項がどうなっていたのかよくわからないが、恐らく長男與四郎が戸籍乗っ取ったんだと思われる
免役対象にならない次男以下が、分家や養子縁組、絶家再興、女戸主への入婿などの手段で戸主や嗣子になろうとし、結果、明治12年には20歳男子人口32万人中、90%近い28万人が免役該当となり、20歳男子の大半が一家の主人かその跡継ぎになっていたそうだ。 ウチの先祖がまさにそれで、