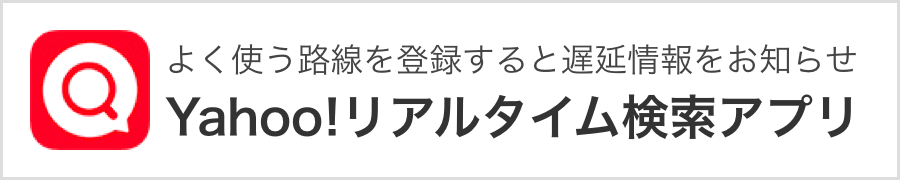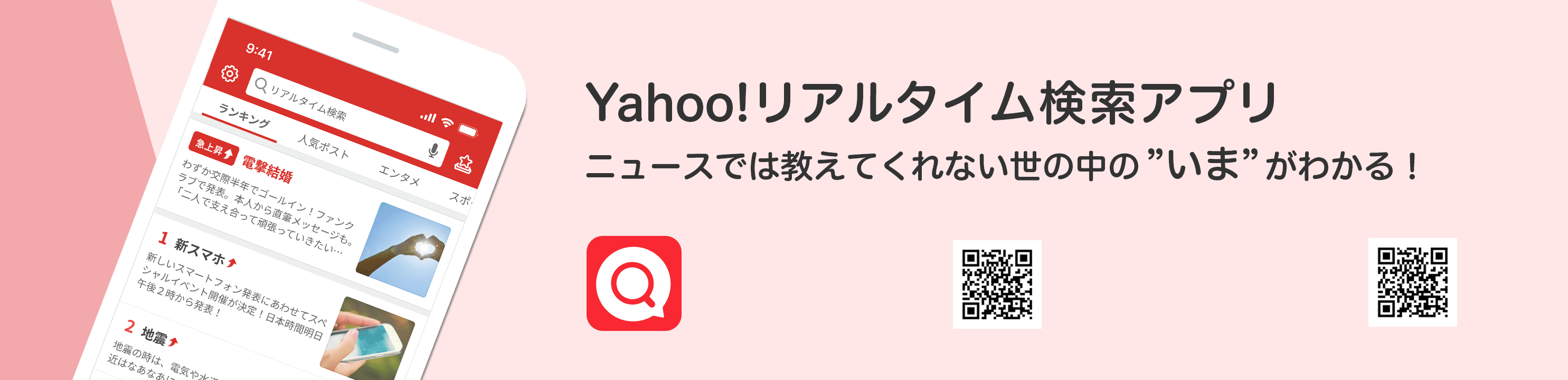- すべて
- 画像・動画
並べ替え:新着順
苫前町古丹別の道道437号羽幌原野古丹別停車場線旧道区間。地味な場所ながらちゃんと道道の痕跡が残っていました。 この辺りの旧道がウネウネとカーブしているのは、三毛別川と古丹別川の旧河道(三日月湖)を極力避けるルートを取ったためでしょうねぇ。 pic.x.com/tkUJZrtik7
前回は真っ暗だった住吉西公園の南にあるちょっと複雑な五叉路は、来た道の左が自然堤防の端を東に向かう古い道、次がその古い道を横切る旧河道の二ヶ領用水井田堀が暗渠になった道で、その次が自然堤防の端を西に向かう道! そして一番右の道が宅地造成で加わった北向きの道になる!#川崎市 #中原区 pic.x.com/hXUzQMvV3F
辺りはもうだいぶ暗くなってきたけれど、住吉西公園の南にあるちょっと複雑な五叉路を越えて、井田と木月の境を南に向かう二ヶ領用水井田堀の暗渠をさらに先に進む! すると旧河道を通る暗渠らしく、五叉路の前で少し右に曲がった後、今度は少し左に曲がりながら尻手黒川道路に出た!#川崎市 #中原区 pic.x.com/D3aR46kJSG
井田の東端に当たる木月との町境を南進する二ヶ領用水井田堀の暗渠が住吉西公園を越えた先では、ちょっと複雑な五叉路を横切る! この五叉路は南側に広がる自然堤防の端を東西に通る古い道に、旧河道を通る堀が暗渠に変わった道が横切り、さらに宅地造成で北向きの道が加わったもの!#川崎市 #中原区 pic.x.com/sEY4hOkTIT
返信先:@chimei_saitama確かに。仰る通り報告書2(1982) p.11 のルビは「こがわばた」ですね。 古谷は北条時代の記録が残るほど歴史が古いうえに、旧河道(荒川・入間川)がこの辺に交錯していた影響もあって、小字もちょっと独特な印象のものがあるように思います。
👣暗渠講座〈稲城・大丸用水〉 ✾素掘りなど 津島神社 旧河道のはざまの微高地近く。自然すぎる素掘り地点。「ここに注ぐ流れは〇〇から来ています」という説明に、おぉ~と繋がる! pic.x.com/USWClw8uaP
空撮:地理:農業土木:農業景観:押付新田・布川の島畑景観(茨城県利根町) 利根川の氾濫原の低平地で、水田に入れる水は水抜きの溝(クリーク)から水を汲み上げるしかなく、微高地は取り残されて畑となった。水田と畑がまだら模様の景観を呈している。 集落は旧河道の自然堤防上に成立している。 pic.x.com/Lhwi6GVqaf
続いて訪ねた、中世には土豪が拠った鬼怒川のデルタ地帯の旧河道を立体視。比高がわずかなので、立体視でも感じにくい。x.com/santetsuzoku/s… pic.x.com/vWKRCabv1X
続いて訪ねた、中世には土豪が拠った鬼怒川のデルタ地帯の旧河道。ちょうど旧河道の真ん中から上流を眺めている。 x.com/santetsuzoku/s… pic.x.com/ZsZSrqZyjJ
「鳥羽淡海」を読む。筆者が鬼怒川のデルタ地帯と呼ぶ地域には、中世の頃、比毛氏・肘谷氏・袋畑氏・伊古立氏が拠り、下妻に入ってきた多賀谷氏と争った記録があるという。このことから、中世のデルタ地帯は土豪が拠ることができるくらいに耕地が開かれていたと推定。 kenzkenz.xsrv.jp/open-hinata/?s…
中世の豪族たちが拠ったデルタ地帯の旧河道を訪ねてみた。 x.com/santetsuzoku/s… pic.x.com/yHAzVXEUIT
「鳥羽淡海」を読む。筆者が鬼怒川のデルタ地帯と呼ぶ地域には、中世の頃、比毛氏・肘谷氏・袋畑氏・伊古立氏が拠り、下妻に入ってきた多賀谷氏と争った記録があるという。このことから、中世のデルタ地帯は土豪が拠ることができるくらいに耕地が開かれていたと推定。 kenzkenz.xsrv.jp/open-hinata/?s…
上富良野町の道道581号留辺蘂上富良野線旧道区間(旧千望峠)。空中写真を見ると、この辺りも旧河道の痕跡がクロップマーク(植物の発育差による模様)としてはっきり出ていますね…! pic.x.com/LO37f4RY3T
治水地形分類図を見ると、長福寺付近にある分水地点の手前の二ヶ領用水井田堀は、左に自然堤防の微高地がある旧河道の東端を通っていて、分水地点から直進する堀はそのまま旧河道の端を進む! これに対して左に折れる堀は自然堤防に入り込むためか、細かい蛇行を見せるのが特徴的!#川崎市 #中原区 pic.x.com/DfBApyA7TK
今年もオオヨシキリたちが盛んに囀る不思議な場所。なぜ不思議かというと、川も池もないのに群生する葭原。 元は溜池でもあったのか?埋められた旧河道なのか?そして豊富な水の供給が絶えずあるということなのか。 pic.x.com/83SWfWAD3H
富山大学五福キャンパスの周辺には井田川や神通川の旧河道が入り組む。戦国時代まで実際に水が流れており、現在の呉羽公園や水墨美術館の池はそのなごりである。学生さんにも通学の折などに見かける堤防状の土盛りや、住宅地の間などに見える段差にはそうした謂れがあると思ってもらえると嬉しいかな。 pic.x.com/CWwqdHlbKD
治水地形分類図で見ると、二ヶ領用水井田堀の上流部は下流側に向かって右が微高地の自然堤防、左が多摩川の旧河道で、堀があるのはたぶん旧河道の端。 右後ろの道と合流するY字路の先で、井田堀の暗渠が道の右端から左端に移るところからは、その流路が自然堤防の上に変わっている!#川崎市 #中原区 pic.x.com/qaehFU5mLE
神通川西岸の井田川左岸、下野・下野新地区には、明治27年の井田川直線化工事により生じた旧河道や自然堤防、微高地が散在する。旧河道とその一帯は、以後水田化と住宅地化が精力的に進められてきたが、流砂主体の自然堤防は水持ちが悪く、現在もなお畑作地にとどまり、強風時には砂塵に悩まされる。 pic.x.com/zXs1DY6CcM
【鶴見川ウォーク_中流_3】 1,2:市ヶ尾駅から離れると長閑な雰囲気に。 3:恩廻公園。ここは鶴見川の旧河道でこの下には洪水時に水を溜める巨大な配管が埋め込まれています。 4:現在の鶴見川との合流地点付近は崖線に大きな樹木が残っており鬱蒼としています。 pic.x.com/0IGgBie2nt