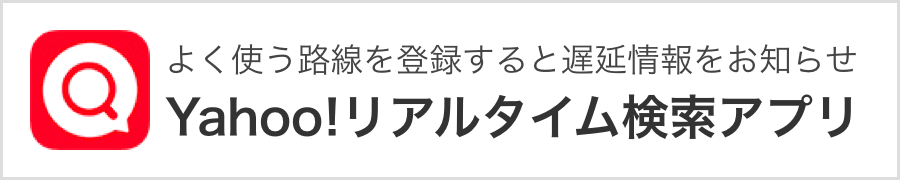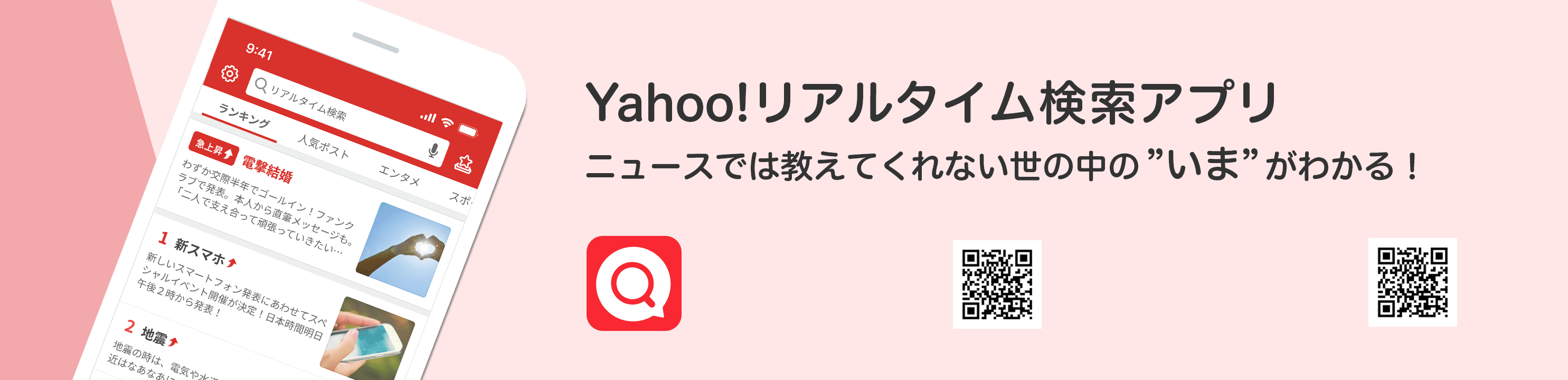- すべて
- 画像・動画
並べ替え:新着順
返信先:@jitsuyo_sosyo最も早い西周中期の金文の頃から声符「虍」がありますね 戦国中期の楚で「虍」が無くなっていて、これが現在の「処」と同じ形のようです 一方、斉や晋、秦といった国では「虍」が残っているように見えます 『説文解字』では「処」の形で載っていて、「處」は惑体(異体字)扱いですね pic.twitter.com/Xwj4Kjhqc2
漢和辞典 毎日読んでも〔得〕構文とかの存在は 永久に知りえない とかいう反論きそう 解字の部分を良く見ろ 段玉裁の〔説文解字註〕と〔康煕字典〕を引いて 比較対象しながら 現代普通話での当該漢字使用の根拠を探れ 〔得了〕〔不了〕の使用の歴史を辿れ
中国関係 『青木正児全集』『訓読説文解字注』『全釈漢文大系』『中国古典文学大系』 日本関係 『漢語文典叢書』『北畠親房公歌集』『古事記全註釈』『武田祐吉著作集』『津田左右吉全集』『天理図書館善本叢書』『本朝文粋註釈』『万葉集大成』『国語学叢書』(東京堂書店)『万葉評釈』(長井金風)
「湾(灣)」は『説文解字』になく比較的後起の字(『廣韻』にはある) 恐らく「彎」から派生して義符「水」が付いた新しめの字(こういうのは声符に意味があるように見える) 「彎」の兄弟のような字 ですから彎曲を灣曲とも書く(海関係でないのに) 昔から側彎を側灣と書くのに抵抗がなかったのでしょう pic.twitter.com/rYHieKjLy6
じゃあ野党も飛び回っている遊説はお遊びか(笑) 説文解字によると、游(遊)は旌旗乃流也とあって、色鮮やかなbannerが流れていく様を示す。そこから他の地に出掛けて行くことを表すようになったのだろう。それが時として楽しいから「遊ぶ」という意味を持ったまでで、外遊には「遊ぶ」の意味はない。
麒麟(きりん) 「麒、麒麟、仁獣也。麋身、牛尾、一角(説文解字)」 麒、麒麟は仁獣である。身体はナレシカ(大鹿・トナカイ?)で牛の尻尾、1本のツノがある。 #ゴールデンウィークSNS展覧会2024 pic.twitter.com/4ho1VZzgny
説文解字に 「嫉。本字は㑵。別字は婦人には嫉妬の情が強いからであろう。」 と、完全にディすられてて草 妬は「婦人、夫を妬(ねた)むなり」もともと、婦人の感情限定を指す言葉だったが、転じて「賢能を憎む」の意に。
漢字学では六書の定義文は、造字法と用字法から成るとされてきた。この通説で注意すべきなのは、六原則の定義文が説文解字の序文に載っているのに対して、造字法という言葉は漢書芸文志の記述「造字之本也」からきているということだ。そして用字法の直接的な根拠となる記述はどこの文献にも存在しない
字注訓については、「銅」の「あかがね」という訓や「鉄」の「くろがね」という訓は『説文解字』『玉篇』の「銅、赤金也」「鉄、黒金也」という語釈を読み下したものだという説が紹介されていた(他には「佃、作田」「宿、夜止」「梢、木末」「源、水本」「証、明」などもあった)
「大きな羊は美しい」、わたしは『白暮のクロニクル』(ゆうきまさみ)で出会ったけど いやあ羊はいいですね、特に大きな羊はいいものです『説文解字』 メェメェ 羊は美しい 義も善もメェー かわいい だがメェーたち案外パワフルなのでコントロールは大変 多岐ボーヨー
返信先:@iru_han2犀とは無関係ですね 説文解字は甲骨文字を知らないので今となっては誤りは多いです ちなみに屖は声符「尸」の形声字ということになってます 「遲」/*l<r>ə[j]/BS 「尸」/*l̥[ə]j/BS pic.twitter.com/jV16KI9GYC
Learn ancient Chinese seal script from the link given below: 《説文解字》中敍“自爾 秦 書有八體:一曰大篆;二曰小篆;三曰刻符;四曰蟲書;五曰摹印;六曰署書;七曰殳書;八曰隸書。” baike.baidu.hk/item/%E7%A7%A6…
「篆書目録偏旁字源碑」北宋時代の石碑で、「説文解字」の部首などを篆書で記し、その下にその音を表わす文字を楷書で記したものです。後半には、この石碑を作った経緯などを記したと思しき序文もあります。 冒頭、「昔秦相李斯...謂之小篆」くらいは読み取れる。 pic.twitter.com/QdLxQTzPIZ
倭(烏禾)、倭(於為)がアワと読むことを証明した 次は、「烏何」がアワと読むか。 烏:安(ア)なり。哀都(アア)切 説文解字より、 孔子:烏が「アーッ」って鳴くから亏(ア)だ。 よってア=烏=亏=於(ア音証明済み) 何 ha(ハ) 烏何(アハ=ワ)となる。 よって、烏何(アワ) すべて、阿波 次は倭(荒外) pic.twitter.com/xkEY5L5Ze8
返信先:@monkey0026書いているとおり説文解字からある説で、古文字学の大御所・裘錫圭さんもその説に則っていて、『中国漢字学講義』でも同説を述べて会意字としています RayNunokawa氏は、「名」に関する典拠が他にないため止むなく同説を取っているのかもしれません(エビデンス優先で)
返信先:@fandake1倭▶︎lead the buddhistであり、 猊下に率う(遵う、したがう) という意味である。 康熙字典に 順猊(貎)と書いてある。 説文解字注(段玉裁) pic.twitter.com/VJ6Uimfb8P
神札保存用の紙袋を作り直した。 「龗」は中国語で「霊」と同じ読み方で、『説文解字』など古籍より龍や神霊の意味がある、龍神にぴったり漢字だね。靇𩆇𩆈𪚙など表記もある。「霝」は独立な漢字としてまた「霊」と同じ読み方で、霊験・(雨など)降るなど意味がある。 pic.twitter.com/zzs70YNeIP
漢字好きにとって「こんな漢字ないよね?」という質問は恐怖なので勘弁してくだしあ 「常用漢字+人名用漢字にはない」「表外漢字字体表の範囲にもない」までなら自信持てるけど、「JIS第3水準にない」は言い切れないし、「説文解字にない」はマジで無理