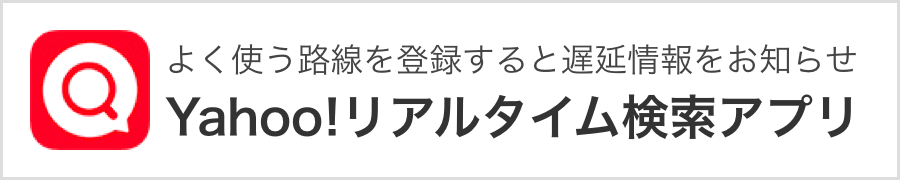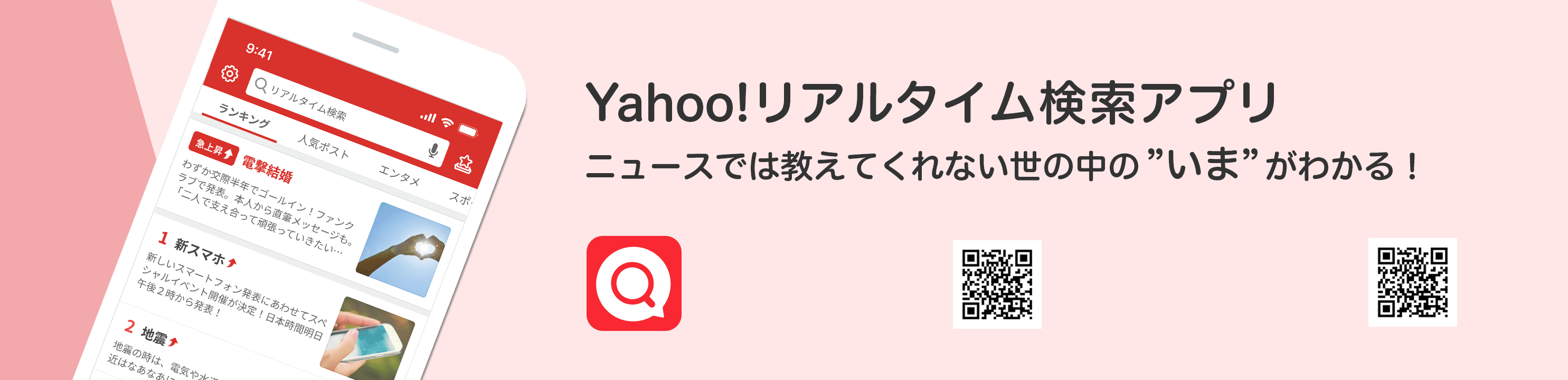ポスト
まず前提として、室町時代の地方の寺社は「商社」としての側面が強かったと思います。江戸時代は年貢が村請中心になりますが、前段階として寺請が多かったのではないかしら。年貢を徴収し、銭にかえ、それらの記録や計算のため読み書き算術を学ばせる。不入権を土台に、経済活動を担っていたのです。
メニューを開くみんなのコメント
メニューを開く
秀吉が寺に入ったのは義父に疎まれたからという逸話もありますが、秀吉の出自が後の渋沢栄一レベルの富農なら、「商社」としての寺社ネットワークとつながりをもち、読み書きや算術を学ぶために寺に入ったと考える方が、後の立身出世を考えても納得度が高いと思えるのですよ。
人気ポスト
学マス、Eエンドまで存在するんだけど流石にここまで見てて辛くならないEエンドは初めてすぎると思うんですけど 小学生のしつけ
犬の詩です
え゚っ
これで一生わろとる
彼女に活動バレて振られそうになったから、 ディズニーランドでメンチ切ってきた。
魚の4コマ「倫理観ある人」
【世界初】「スライスレモン入り」レモンサワー缶、11日から1都9県で発売 news.livedoor.com/article/detail… アサヒビールの「未来のレモンサワー」は、缶を開けると炭酸の力でスライスレモンが浮かび上がってくる新商品。2021年に発売した「生ジョッキ缶」の技術を応用して開発されたという。
フルーツゼリーもお好きなだけどうぞ!って言ったら、掴み取りされた(笑)
お出掛けの際、3歳になる息子が急に走り出す事が多くなりました。そんな時、保育園で教わった「振りほどかれない手の繋ぎ方」を実践してみました。写真のように手を繋ぐことで、子供の拳をしっかり掴むことができ安全に外出することができます。普段の外出時や災害時の避難の際にも有効です。
トレンド15:20更新
- 1
キングカメハメハ
- コントレイル
- 顕彰馬
- ディープインパクト
- JRA
- 2024年度
- 2
アニメ・ゲーム
桐生一馬
- 竹内涼真
- 龍が如く
- 全裸監督
- 真島吾朗
- 命をかけて
- Prime Video
- 実写ドラマ化
- 実写ドラマ
- Beyond
- Amazon Prime Video
- ドラマ化
- 3
ITビジネス
Google従業員
- 非公開動画
- 従業員
- YouTube
- 4
ITビジネス
アダルトコンテンツ
- シャドウバン
- 5
ITビジネス
AIアートスクール
- 小学生向け
- VROOM
- 吐き気がする
- 生成AI
- 問題がある
- AI
- ショートカット
- 6
アニメ・ゲーム
スト6半額
- 世界中を
- ストリートファイター6
- スト6
- レジェンズ
- 67%
- 7
エンタメ
カップリング曲
- IMP.
- Number_i
- 8
エンタメ
真島の兄さん
- 桐生ちゃん
- 実写化して
- 北村一輝
- また実写化
- 真島さん
- 岸谷さん
- 岸谷五朗
- 9
旧国鉄客車を改装のカフェ
- 価値失われた
- 旧国鉄客車
- 鉄道ファン
- 鉄オタ
- 毎日新聞
- プレハブ
- 10
ニュース
中国国営企業
- ロゴ問題
- 一般国民
- 当然の結果です
- 河野大臣
- 中国国営