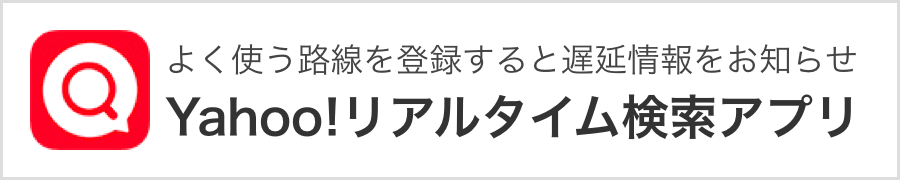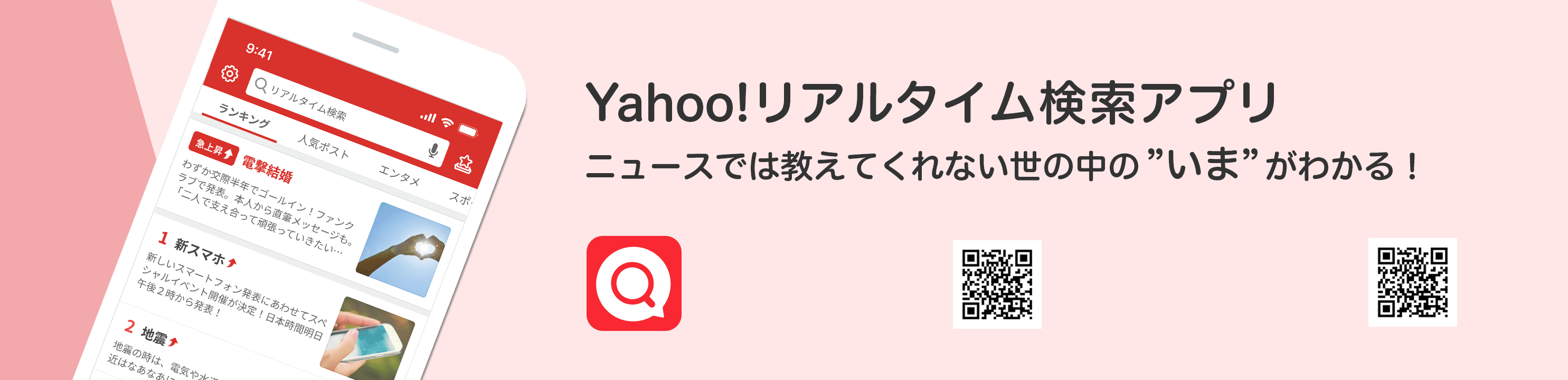ポスト
みんなのコメント
メニューを開く
専門家が調べていると思うけど家の辺は扇状地なので数十㌢下は砂利ですが、畦塗りとかすれば別に水は漏らず溜まったままです。まぁ田圃と用水の様に水量の多い所ではは比べようもないでしょうが。 x.com/mysterious_bow…
こうした素掘りの灌漑施設の水が、どうして地面に吸収されてしまわないのか、というのが今回の発掘調査で出てきた謎なんです。調査中の溝とその周囲にかなりの雨が降っても、その水はどんどん地面に吸収されてしまって、流れるどころか溝に溜まらない。地下水になってしまう。利用されていた頃、どうや…
メニューを開く
江戸時代の玉川上水での水喰らい土の話は参考になりますでしょうか? 発掘地点での話に絞ると 発掘調査された場所は何処かで使用されなくなってるので、貴重な粘土層は持ち去った可能性も有ったりしないでしょうか?今でも田圃に貯まった粘土層は売買されますし jkeng.co.jp/column/column0…
メニューを開く
古墳時代前期の高崎や前橋台地の地下水の帯水層は、集落遺跡の井戸の深さで推定できますが自由地下水の高さは現在よりも高かった可能性があります。現在の水系の祖型は5世紀末のFAの噴火で変更されたので、それ以前は場所によって違います。去年の紀要に書いたので近い内にpdf公開される予定です。
人気ポスト
朝敵ってやっぱ恐ろしいほど面子豪華だな...
"ねこけし"はね、影までかわいいんだよ。
【朗報】夫、牛乳と乳飲料の違いを完全に理解!!!!ありがとう!!ありがとう!!
猫が赤ちゃんの頃、お布団かけてあげると速攻で「スヤァ…😴」してたのマジで可愛すぎたな…
(お前…絶対文字が読めてるだろ…)
ほら言うた通りキャベツの相場が大暴落。 1玉1000円のキャベツが200円切りました。大玉5玉入りで箱1000円切りました。20ケース頼まれました。高い時だけで無く安い時も報道して欲しいって千の夜をこえてあなたに伝えたい。
いい大人なのに欲しいよ
これ覚えておくと、料理する時に困らないよ。食べ合わせが悪い食材もあるから要注意!
母にビデオ電話すると、毎回これはオンなのかオフなのかわからなくなると相談される。どんなUIが最適なのか。
トレンド15:29更新
- 1
アニメ・ゲーム
ショートアニメ
- グラモス
- ショート
- 2
アニメ・ゲーム
ブレイブルー
- ギルティギア
- アニメ化発表
- アニメの話
- ギルティ
- アニメ化
- 好きなアニメ
- 動画配信サービス
- 無料視聴
- 3
ロクシタン
- SEVENTEEN
- 4
Key新作
- アネモイ
- anemoi
- Key
- 5
那覇市職員
- メンタル不調
- 93人
- 業務に対する不安
- 倒れる寸前
- 沖縄タイムス
- 悲しいニュース
- 適応障害
- 那覇市
- 6
アニメ・ゲーム
ファミコン四十年生
- ファミリーコンピュータ
- ファミコン
- ファミコン40周年
- 7
アニメ・ゲーム
サンジゲン
- ギルティギア
- テレビアニメ
- アニメ化
- バンドリ
- 8
ニュース
JCBカード
- VISAカード
- VISA
- 時間の問題
- メロンブックス
- 思いますので
- 9
グルメ
サーティワンのポップ10
- ポップ10
- 10
エンタメ
NAYEON
- ABCD
- NA