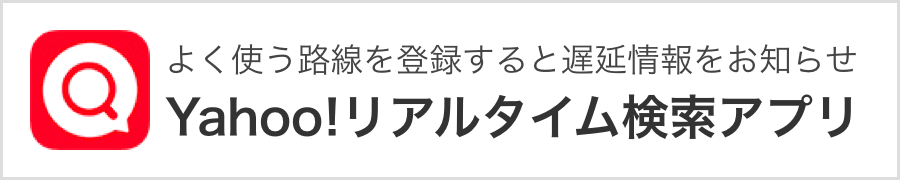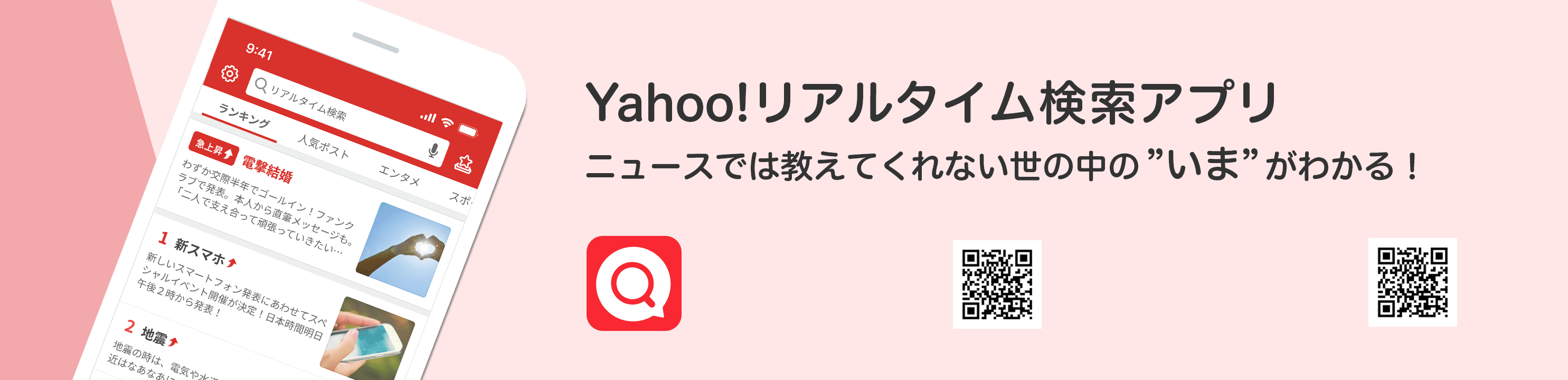ポスト
例えば「Maj7」。 長7度(転回で短2度)つまり「不協和音程」を含む。 伝統的な対位法でも和声でも、7度には「解決」が必要。 が、ボサノヴァだろうがフレンチポップスだろうが「Maj7」の7度は しばしばそのまま放置され「解決」されない。 が、そこに「不協和」感はあるだろうか。 x.com/tadzi0/status/…
メニューを開くこの分類は、対位法や和声で、音の動き方をコントロールするためのベースになっている訳です。 どこで線引きをして、どういうルールで音を動かすか、は、時代で変化してきた部分がある。 時代様式によって、どの「不協和」をどう許容するかは違う。絶対的なものがある訳ではない。 x.com/tadzi0/status/…
みんなのコメント
メニューを開く
重要なのは、その様式的な音環境。 全く同じ音が、様式的な音環境によって、「不協和」感を感じることもあれば 感じないこともある。 「様式的な音環境」如何なのだ。 例えば、ショパン作品の音環境で、Maj7が放置されていたら、気持ち悪い。 有名なEs-durのノクターン、最初のフレーズ末尾(続
人気ポスト
私の寝る場所が無い❗😭😭😭
こんなんタトゥーにするわ
スタイル良すぎな 後ろから抱きつきたい
26歳と28歳の部屋の変化。
左が数年後に右になるんだから子どもって怖いよな
え???この本2005年刊行なんだけど、 19年前のトリニティリングLMって15万円だったの…?? 現在55万円なんだけど… いくら値上げでも3倍以上は流石におかしいのでは🥲
病院にあった七夕の短冊
こういう動画見て、「シアトルやばい」「サンフランシスコ終わった」とか言うのは間違ってて、たとえばこれはフィラデルフィアだけど、アメリカのそこそこレベルの都市はだいたいどこもこんなエリアがある。
この感覚のやつが校長やら教育委員会にいると、まさに現場は地獄。 感覚が狂ってる。
トレンド10:14更新
- 1
エンタメ
恋を知らない僕たちは
- コイスルヒカリ
- 大西流星
- 主題歌
- 発売決定
- 2
エンタメ
茨田りつ子
- 茨田さん
- りつ子さん
- 茨田
- 茨田りつこ
- りつ子
- 愛のコンサート
- クロスオーバー
- 福来スズ子
- 3
グルメ
チョコミン党
- 4
スポーツ
25号
- 10試合連続
- 10試合連続打点
- 球団新記録
- 先頭打者ホームラン
- 大谷翔平が
- 2試合連続
- 10試合
- 100安打
- 2試合連続先頭打者ホームラン
- 先頭打者
- Dodgers
- ドジャース・大谷翔平
- ドジャース
- ホームラン
- Shohei Ohtani
- 26度
- 大谷翔平
- 連続打点
- 5
エンタメ
直系血族
- 民法730条
- ロジック
- 6
エンタメ
KATUJI
- 桶ット卓球
- 桶ット
- ふらわぁ桶ット
- KATUJIスマッシュ
- LEOくん
- KATSUJI
- 純喜くん
- カツジ
- 純喜
- レオくん
- ふらわぁ
- 世界レベル
- 目がバキバキ
- Leo
- めっちゃ盛り上がった
- 7
ITビジネス
冷笑主義
- 迷惑ボランティア
- 蔓延して
- 迷惑系議員
- 8
アニメ・ゲーム
ハイゼンスレイ
- METAL ROBOT魂
- ガンダム
- MS
- 9
エンタメ
矢花くん
- 長瀬くん
- TOKIO
- 事務所の人
- ブログ
- 10
エンタメ
ご機嫌よう
- ご機嫌よう!
- よねさん
- 大庭家