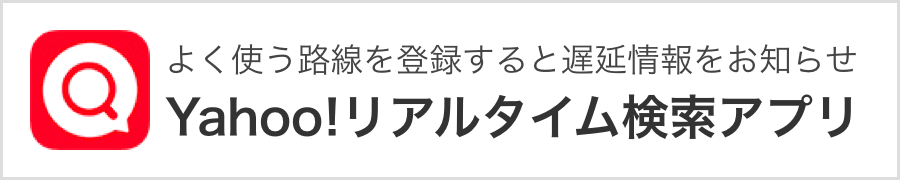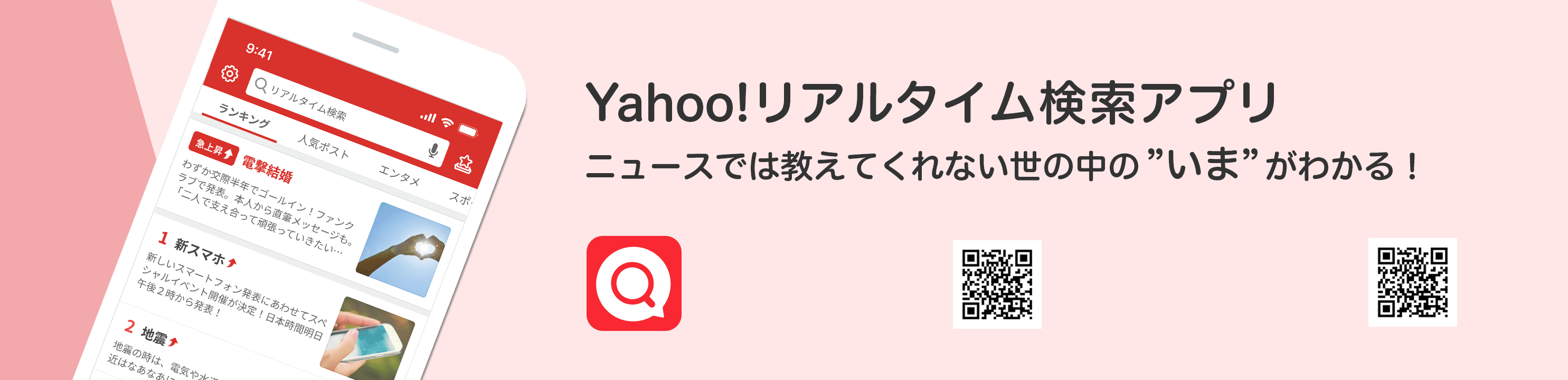- すべて
- 画像・動画
並べ替え:新着順
#11月23日 の #誕生木 【シラカシ】(おまけ) 伐採直後の材が白いことから「白樫」と呼ばれる。別名のクロガシは樹皮の色が由来。材は建築材、船舶材、器具等に利用される。 pic.x.com/Yuy2dv1Col
#11月23日 の #誕生木 【シラカシ】 分類はブナ科 コナラ属 常緑高木。別名はクロガシ、ホソバガシなど。開花は4~5月頃、雌雄同株で葉脇の花穂に花をつけるが剪定管理される場では見る機会は少ない。ドングリができる木として知られ、防風林や垣根、公園樹等で見る機会が多い。 #誕生日 pic.x.com/3GK0Q23VF9
#11月22日 の #誕生木 【サルトリイバラ】(おまけ) 根茎は薬用、葉は柏餅などを包む葉の代用、赤い実はリース飾りなど様々な用途で使用される。名の由来は棘のあるつるがサルをも捕まえるという喩えから。 pic.x.com/AIoVUBNYSg
#11月22日 の #誕生木 【サルトリイバラ】 分類はサルトリイバラ科 シオデ属 落葉小低木 つる性。別名は山帰来、カカラ、ガンタチイバラなど。開花は4~5月頃、雌雄異株で黄緑の小花が咲く。後につく実は冬にかけ赤く熟す。葉は独特の香りがあり、若葉は饅頭や餅の包み等に用いられる。 #誕生日 pic.x.com/hIqkD8gJUm
#11月21日 の #誕生木 【ムラサキシキブ】 分類はシソ科 ムラサキシキブ属 落葉低木。別名はタマムラサキ、ムラサキシキミなど。開花は6~7月頃、葉脇の花柄に淡い紅紫の小花が咲く。後につく実は黄葉にあわせ紫に熟す。元は玉紫やムラサキシキミと呼ばれたが、紫式部にあやかり改名された。 #誕生日 pic.x.com/p4qiCRHoDn
#11月20日 の #誕生木 【カラマツ】 分類はマツ科 マツ属 落葉高木。別名は落葉松、富士松、日光松。開花は4~5月頃、雌雄同株で同じ木に雌雄の花が咲く。後につく球果は秋頃に黄褐色に熟す。日本の松で唯一の落葉性で、名の由来も落葉して葉が無くなることからなど諸説ある。 #誕生日 pic.x.com/CAQFFdtDtW
#11月19日 の #誕生木 【トウカエデ】 分類はムクロジ科 カエデ属 落葉高木。別名はサンカクカエデ。開花は4~5月頃、枝先の花序に淡い黄色の雄花と両性花を咲かせる。名は「唐(中国)の楓」であることから。紅葉の鑑賞価値が高く頑丈なため、街路樹などで見る機会が多い。 #誕生日 pic.x.com/acVxdt2emm
#11月18日 の #誕生木 【マルバノキ】 分類はマンサク科 マルバノキ属 落葉低木。別名はベニマンサク。開花は10~12月頃、葉で隠すように花弁の細い赤紫の花を咲かせる。秋頃には一本の木で赤、黄、緑の3色が入り混じる紅葉が目を惹く。名は葉形が由来だが、新葉の頃はハート型をしている。 #誕生日 pic.x.com/baB8bM97Jj
#11月17日 の #誕生木 【クコ】 分類はナス科 クコ属 落葉低木。別名はシネンセス、ヌミクスリ。開花は7〜11月頃、葉の付け根に薄紫の花が垂れ下がるように咲く。赤い卵型の実は翌年の花期に熟すため、花と一緒にできるように見える。川の土手や海岸近くで見る機会が多い。 #誕生日 pic.x.com/hYBEZPxKo8
#11月16日 の #誕生木 【イチョウ】 分類はイチョウ科 イチョウ属 落葉 高木。別名はギンナン、ギンナンノキ。開花は4~5月頃、雌雄異株でどちらも花弁のない花を咲かせる。後につく実は中の胚乳が食用のギンナンとなる。名の由来は中国名「イーチャオ」が転訛したとされる。 #誕生日 pic.x.com/sgxIggKwOb
#11月15日 の #誕生木 【オトメサザンカ】 分類はツバキ科 ツバキ属 常緑小高木。サザンカに多数ある栽培品種の一つでカンツバキ群という遅咲きの分類に入る。花は桃色で「千重咲き」という花弁がバラのように重なった花をつける。遅咲きだが寒さにはあまり強くない。 #誕生日 pic.x.com/xwInCFsTh8
#11月14日 の #誕生木 【フウ(タイワンフウ)】 分類はマンサク科 フウ属 落葉高木。別名はフウ、サンカクバフウ、イガカエデなど。開花は3~4月頃、雌雄同株で黄緑の小花が球形に集まって咲く。後につく実は冬にかけ褐色に熟す。紅葉の鑑賞価値が高く、街路樹や公園等で見る機会が多い。 #誕生日 pic.x.com/yqwxZYVu4C
#11月13日 の #誕生木 【ナナミノキ】 分類はモチノキ科 モチノキ属 常緑高木。別名はナナメノキ、カシノハモチ。開花は6月頃、葉脇に薄紫の小花を咲かせる。後につく楕円形の実は冬に赤く熟す。名は美しい実のなる木という意味合いから「七実の木」「長実の木」などが語源とされる。 #誕生日 pic.x.com/XJQkvidX6c
#11月12日 の #誕生木 【カンボク】 分類はスイカズラ科 ガマズミ属 落葉小高木 。別名はケナシカンボク。開花は5~7月頃、枝先の花序に乳白色の小花が密生する。花の周りで目を惹くのは花弁ではなく装飾花。民間療法に用いられ、人に肝要な木とされたことが名の由来という説がある。 #誕生日 pic.x.com/q9M9wl0Zgo
#11月11日 の #誕生木 【シラキ】 分類はトウダイグサ科 シラキ属 落葉中高木 。別名は白乳木、猛樹。開花は5〜7月頃、葉脇の花序に雌雄の花が穂状に咲く。樹皮など全体的に白く、傷付けると白い乳液が出るのが特徴。名の由来は灰白色の樹皮や材の白さからなど諸説ある。 #誕生日 pic.x.com/QePAZJPmYZ
#11月10日 の #誕生木 【アメリカフウ】 分類はマンサク科 フウ属 落葉高木。別名はモミジバフウ。開花は4月頃、雌雄同株で雄花は房状で上向き、雌花は球状で垂れ下がるように咲く。紅葉は色とりどりで華やかだが、葉が落ちるのが早く鑑賞期間は短い。葉の形から別名の方が知名度は高い。 #誕生日 pic.x.com/y7CVQT4f6X
#11月9日 の #誕生木 【ベニカエデ】 分類はムクロジ科 カエデ属 落葉高木。別名はアメリカハナノキ、ルブルムカエデ。開花は3~4月頃、雌雄異株で赤い小花が枝に集まるように咲く。西洋カエデの品種だが日本のハナノキによく似ている。名の由来は紅葉で葉が真紅に染まることから。 #誕生日 pic.x.com/bLgFcpC9GD
#11月8日 の #誕生木 【クロガネモチ】 分類はモチノキ科 モチノキ属 常緑高木。別名はフクラシバ、フクラモ、イモグス。開花は5~6月頃、雌雄異株で葉脇に紫がかった乳白色の小花が密生する。後につく実は冬頃に赤く熟す。名はモチの仲間で葉が乾くと鉄色になることが由来とされる。 #誕生日 pic.x.com/ZRv4I5R7IC
#11月7日 の #誕生木 【カツラ】 分類はカツラ科 カツラ属 落葉高木。別名はマッコウノキ、カモカツラ、醤油の木など。開花は3~5月頃、雌雄異株でそれぞれ花弁のない花を咲かせる。葉がしおれると醤油煎餅のような匂いがするのが特徴。都心での植栽も多く、日本の銘木として知られる。 #誕生日 pic.x.com/7YaBihtB5M
#11月6日 の #誕生木 【サザンカ】 分類はツバキ科 ツバキ属 常緑小高木。別名はヒメツバキ、コツバキ、コカタシなど。園芸品種が300以上、それぞれで開花時期や花の様子は異なる。原種は椿に似るが白や薄桃の一重咲きで花弁から散る。名の由来はツバキの漢名「サンサカ」が転訛したとされる。 #誕生日 pic.x.com/ZpAj2zKK0x
#11月5日 の #誕生木 【ハウチワカエデ】 分類はカエデ科 カエデ属 落葉高木。別名はメイゲツカエデ。日本の楓で最も葉が大きい種。開花は4〜6月頃、枝先に紅白色の花が垂れ下がるように咲く。名の由来は葉形が鳥の羽や団扇に見えることから。印象的な花や紅葉から庭木として見る機会も多い。 #誕生日 pic.x.com/wMhL0RnkW9
#11月4日 の #誕生木 【カリン】 分類はバラ科 カリン属 落葉高木。別名はカラナシ、ホンカリン、アンランジュ、マルメロ。開花は3~5月頃、桃色の花が一輪ずつ咲く。実は秋頃に黄色く熟すが、見た目に反して生食には向かない。名の由来は木目が花櫚(インドシタン)に似ることからとされる。 #誕生日 pic.x.com/BhUpBJkirF
#11月3日 の #誕生木 【カイノキ】 分類はウルシ科 カイノキ属 落葉高木。別名はランシンボク、コウレンボクなど。開花は4~5月頃、雌雄異株で葉脇の花序に小花が円錐状に垂れ下がるように咲く。後につく実は秋頃に濃い紅色に熟す。紅葉は環境次第で赤にも黄にも変化する。 #誕生日 pic.x.com/vrBjhqy7Y6
#11月2日 の #誕生木 【ガマズミ】 分類はレンプクソウ科 ガマズミ属 落葉低木。別名はヨツズミ、シモフリグミなど。開花は5~6月頃、枝先の花序に小花が集まるように咲く。後につく実は秋頃に赤く熟す。名の由来は鎌柄など農具の材に使われたこと、実の強い酸味からなど諸説ある。 #誕生日 pic.x.com/sJyCswyBNj
#11月1日 の #誕生木 【イロハモミジ】 分類はカエデ科 カエデ属 落葉高木。別名はカエデ、モミジ、イロハカエデなど。カエデの代表種の一つで日本の秋の象徴とされる。開花は4~5月頃、雌雄同株で深紅の小花が垂れ下がるように咲く。後につく実は夏頃に赤く熟し翼が目立つようになる。 #誕生日 pic.x.com/6Tl5WIgqnU
#10月31日 の #誕生木 【マメガキ】 分類はカキノキ科 カキノキ属 落葉高木。別名はシナノガキ、ブドウガキ。開花は6月頃、雌雄異株で葉の付け根に乳白色の雌花、赤みのある雄花を咲かせる。後に柿に似た小ぶりな実が枝に鈴なりにつく。この実は完熟しても渋みがあり食用には向かない。 #誕生日 pic.x.com/2Wq8KtnCNl
#10月30日 の #誕生木 【ナツヅタ】 分類はブドウ科 ツタ属 落葉つる性。別名はオニヅタ、ニシキヅタなど。開花は6〜7月頃、枝の節から伸びた花序に黄緑の小花を咲かせる。後につく実は冬頃に藍黒色に熟す。抜群の繁殖力と耐性が特徴。紅葉が美しく人気があるが、冬は蔓のみとなる。 #誕生日 pic.x.com/9bOTlbZ8Cn
#10月29日 の #誕生木 【ハクサンボク】 分類はレンプクソウ科 ガマズミ属 常緑小高木。別名はイヌデマリ、ヤマテラシなど。開花は3~5月頃、枝先の花序に白い小花が集まるように咲く。後につく実は冬頃に赤く熟す。主に西日本に自生が多く、庭木とされることも多い。伊勢神宮のものが有名。 #誕生日 pic.x.com/AGCa7XhM7J
#10月28日 の #誕生木 【ベニシタン】 分類はバラ科 シャリントウ(コトネアスター)属 常緑・半常緑低木。開花は5~6月頃、葉脇に淡い紅色や白の小花を咲かせる。後につく実は秋頃に濃い紅色に熟す。名の由来は赤い実が木を覆う様子を紅色の染料「紫檀の木」になぞらえつけられたとされる。 #誕生日 pic.x.com/0dlYGM6wY2
人気ポスト
初対面の男にバキみたい体型だねって言われた女です
【告白】宮野真守、声優5年目頃の月収明かす「バイト抜いたらこれぐらい」 news.livedoor.com/article/detail… 宮野は「6万4000円」と言い、「バイト抜いたらこれぐらいだった」とした。仕事は「役はもらえないけど、その他大勢のガヤで入ってくる、みたいな。エキストラに近い感じの」と振り返った。
【悲報】年末のイタリア旅行、フライトスケジュールが4日後に変更となり終了…
セブンイレブンやっちゃってるねこれ……
渋滞で苦しむ車を見下しながら酒飲むわよ
クリスマスツリーのクッキー、焼く前🎄
「AIに奪われない職」就活生も意識 4割が志望変更、1116人調査 nikkei.com/article/DGXZQO… #労働臨界 #日経_連載
深夜のジムまじこれ
さっき外の人が笑ってたのはこれかww
絵なんて中学校以来描いたことのなかった旦那が、百均で絵の具と筆買って、面会後ハウスで黙々何かしてるなと思ったら、病室からの夕暮れ描いてた。 私はど素人の割にはうまいと思ったんだけど、本人曰く「みんなこのくらい書けるやろ、普通や」だそう、、
SNSのバズまとめ
SNSのバズまとめ一覧